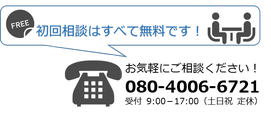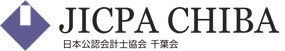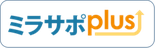生成AIの普及に伴う電力需要の増大とその影響
2024年4月12日
生成AIの急速な普及により、大量のデータを処理するためのデータセンターの需要が世界中で高まっています。データの計算や保存を行うデータセンターを新設する企業が相次ぎ、日本では2050年に電力の消費量が4割弱増えるとの予測があります。2050年までに電力消費が最大で37%増加すると予測されています。この増加は、生成AIによるデータセンターの電力需要が主な要因です。日本政府は国内でのデータセンター建設を促進しており、米マイクロソフトなども大規模な投資を行っています。しかし、この電力需要の増加は、2050年の温暖化ガス排出量実質ゼロの目標に影響を与える可能性があります。政府は将来のエネルギー政策の見直しを予定しており、再生可能エネルギーや原子力発電の再稼働が焦点となっています。技術進展を含めた多様なシナリオを想定した検討が重要視されており、将来の電力供給の安定に向けた解決すべき課題は多いです。

日銀の新展開: マイナス金利の解除と緩和政策の転換点
2024年3月26日
日本銀行は19日の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を終了し、政策金利を0〜0.1%程度に引き上げることを決定しました。また、長短金利操作(YCC)や上場投資信託(ETF)などのリスク資産の買い入れ終了も決め、日銀の大規模緩和政策は大きな転換点を迎えました。この決定は、物価2%目標を持続的かつ安定的に達成できる見通しが立ったため、17年ぶりの利上げとして行われました。マイナス金利政策の終了後も緩和的な金融環境が続くことが予想されます。
日銀は2016年にマイナス金利政策を導入し、金融機関の日銀当座預金にマイナス0.1%の利率を適用していました。しかし、新たな金融枠組みにより、政策金利の誘導目標を変更しました。また、YCCも撤廃し、長期国債の買い入れを現在の月間約6兆円程度で継続する方針ですが、市場の状況に応じて柔軟に調整します。
ETFや不動産投資信託(REIT)の新規買い入れも終了し、これらのポリシーの変更は日銀が持続可能で安定的な2%の物価目標達成に向けて緩和策の修正を検討してきた結果です。現在、消費者物価指数の前年同月比上昇率は2%を超え、物価上昇の要因は一過性のものから人件費などに移っています。このような背景のもと、日銀は物価2%目標が持続的かつ安定的に達成可能と判断し、マイナス金利の解除を含む現在の金融政策の枠組みが役割を終えたと結論付けました。

GDP改定値発表:企業投資がけん引する経済成長の兆し
2024年3月15日
内閣府は2023年10月から12月の国内総生産(GDP)改定値を発表し、物価変動を除いた実質の季節調整値は前期比0.1%増、年率換算で0.4%増と、速報値から上方修正されプラス成長となりました。このプラス成長は2四半期ぶりで、企業の設備投資が大幅に伸びたことが主な要因です。特に、金融・保険業を除く設備投資は、季節調整後に前期比10.4%増となり、自動車や半導体関連の生産体制強化、非製造業のソフトウエア投資が成長を支えました。
一方で、個人消費は前期比0.3%減と、引き続きマイナス成長を記録しました。エアコンや水産関連の加工食品の落ち込みが影響し、冬物衣料の不振や外食の伸び悩みも見られました。民間在庫の寄与度は下方修正され、在庫の取り崩しが進んだことが示されました。また、住宅投資や公共投資も減少を続けています。
輸出は前期比2.6%増、輸入は1.7%増と安定しており、外需は経済成長をサポートしています。名目成長率も速報値から上方修正され、前期比0.5%増、年率で2.1%増となりました。2023年の暦年成長率は実質が前年比1.9%増、名目が5.7%増で、経済全体の堅調な拡大が見られます。設備投資の伸びが経済の成長をけん引している一方で、個人消費の弱さは引き続き課題となっています。

2024年度税制改正:日本、仮想通貨・トークン保有の課税ルールを見直し
2024年1月30日
日本政府は2024年度の税制改正大綱で、ブロックチェーン企業や投資家が仮想通貨やトークンを保有する際の課税ルールを見直しました。従来、これらの保有に対しては期末時点での時価評価に基づき法人税が課されていましたが、改正では短期売買目的でない場合、時価評価から除外されることになりました。
この改正は、日本のブロックチェーン企業や投資家が海外に流出する現状を受けてのもので、日本におけるWeb3企業との協業や市場形成を促進する目的があります。しかし、Web3企業の海外流出が完全に止まるかは不確かであり、ドバイやシンガポールなど他国の誘致競争に対抗することが求められています。

岸田首相、税収増に伴う所得税減税を提案
2023年10月20日
10月20日、岸田文雄首相は税収増を国民に還元するための期限付きの所得税減税を検討するよう与党幹部に指示する方針を示しました。首相は「国民への還元については早急に具体化していきたい」と述べ、自民党の萩生田光一、公明党の高木陽介両政調会長らとの会談を予定しています。税収増の一部を国民に還元する方策は「一時的で限定的な還元策」と位置づけられ、23日の所信表明演説で公表される予定です。
また、2024年度の与党税制改正大綱の中で具体的な方針が固められる見込みです。政府・与党は物価高騰対策として低所得者向け給付金やガソリン代補助の延長を盛り込む方向で調整中で、中間層も含めた所得税の減税を検討しています。
22年度の税収は前年比6兆円増の71.1兆円となり、首相は税収増を国民に還元すべきだとの立場を明らかにしています。政府はデフレ脱却に向けた対策が必要とし、経済対策では物価高対策と供給力強化が重点とされる見込みです。

法的効力を持つデジタル遺言書
2023年10月4日
法務省は、デジタル技術を利用して遺言書をオンラインで作成・保管できる新制度の研究を始めると発表しました。10月には、この新制度の導入に関する有識者の研究会の初会合を開催する予定です。目的は、インターネットを利用して法的に有効な遺言書を簡単に作成・保存できる制度を創設することで、デジタル社会に適した円滑な相続を実現することです。
現在、法的効力を持つ遺言書には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。新提案の中で、自筆遺言をパソコンやスマートフォンで簡単に作成し、クラウド上で保管する方法が検討されています。デジタル化することで、専門知識がない方でも遺言書の作成が容易になりますし、ブロックチェーン技術を活用すれば、改ざんのリスクも減少します。
海外の事例を見ると、米国では19年に電子遺言書法を制定し、電子署名があればデジタル遺言が認められるようになっています。一方、ドイツやフランスなどでは、デジタルや録音の遺言はまだ認められていない国も存在します。遺言書は非常に重要な文書であり、本人が亡くなった後にその意志を確認するものなので、電子化に関する議論は慎重に行われています。
日本政府は、このような国際的な事例や意見を参考にしながら、新制度の安全性や効果性を確保する方向で検討を進めていく予定です。

日本の大手銀行がデジタル通貨に注目
2023年9月6日
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)とみずほFGが、企業間の決済に使うデジタル通貨で連携します。2024年にはMUFGの三菱UFJ信託銀行の共通インフラでデジタル通貨が発行される予定で、みずほもこの枠組みに参加します。このデジタル通貨は瞬時に決済ができ、コストはほぼゼロになるため、高コストや複雑な貿易決済を効率的に行えることが期待されます。
三菱UFJ信託は新会社「プログマ」を設立する予定で、デジタル通貨やデジタル証券の発行インフラを担当します。このプロジェクトには3メガバンクグループやJPX総研、NTTデータなどが出資します。みずほ銀行もプログマの枠組みに参加し、デジタル通貨の利用可能な分野を探求します。また、三井住友FGは不動産を裏付けにしたデジタル証券の利用を検討中です。
各行が発行を考えているのは「ステーブルコイン」と呼ばれるデジタル通貨で、その保有には法定通貨の保有が義務付けられています。日本では、改正資金決済法により、このステーブルコインの発行は特定の金融機関に限られています。
ステーブルコインの最大の特徴は、ブロックチェーン上での迅速な決済と、取引情報を組み込むことができる点です。これにより、商品の受け渡しと決済が同時に行えます。特に複雑な貿易決済において、このデジタル通貨は大きな効率化が期待されます。
現在の国際送金は、Swiftシステムを利用して行われることが多く、送金には2営業日以上かかることもあります。また、手数料も約10%と高いため、貿易のコストが増加しています。新しいデジタル通貨を使用すれば、これらのコストや時間を削減できることが期待されます。銀行は、送金手数料の代わりに、ステーブルコインの裏付けとしての法定通貨を運用して収益を得る予定で、具体的なサービス料の設定は今後検討されます。

2024年度予算: GXへの2兆円超投資と日本の脱炭素戦略
2023年8月23日
2024年度の予算の概算要求において、日本政府は脱炭素を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)に2兆円以上を要求しました。このうち1.2兆円は2024年度の予算として計上され、残りは次の3〜5年間の予定です。主に、電池、半導体、水素関連機器の国内生産支援や、EVや再生可能エネルギー機器への投資、次世代原発の研究開発、脱炭素分野のスタートアップの育成、そしてEVとFCVの普及促進が挙げられております。さらに、生産プロセスの脱炭素化や持続可能な航空燃料の支援に関する取り組みも検討されております。国際的には、米国やEUも大規模な脱炭素投資を進めており、日本もこれに続いて10年間で150兆円以上の投資を目指しています。政府はまた、GX経済移行債を発行する計画もあり、20兆円の支出を目指しています。新型コロナウイルスや国際的な政治的緊張を背景に、日本は国内生産と米国やヨーロッパとの協力を重視する方針を示しています。

日本の暗号資産取引業界、税制改革への要望書を提出
2023年8月4日
日本の暗号資産に関する自主規制団体である日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と、業界団体の日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、来る2024年度の税制改正に向けた具体的な要望書を金融庁にご提出したことが31日に明らかになりました。
要望書の中心的な内容としては、現在我が国で暗号資産(仮想通貨)に対して適用されている、最大で55%にも達する総合課税を、英国や米国などと同じように一律の20%にするよう提案しています。これにより、暗号資産の取引や保有が税制上の負担から解放され、より一層の発展が期待できるとの観点からの提案となります。
さらに、同時に次の3年間にわたる損失繰り越し控除の適用を訴えています。これは、投資による損失を繰り越して、翌年度以降の所得税から差し引くことができる制度です。また、デリバティブ(金融派生商品)取引に対する税制改正も求めており、現物取引だけでなく先物などの仮想通貨デリバティブ取引に対する適切な税制が求められています。
その他にも、企業が保有する暗号資産について、期末での時価評価による課税からの除外を求めています。これは、企業が短期売買目的以外で保有している仮想通貨について、期末での時価評価による課税から除外するというもので、ベンチャーキャピタルが企業発行の仮想通貨を保有したり、非代替性トークン(NFT)事業を営む企業が決済目的で仮想通貨を保有したりする際の障害を取り除くことを目指しています。
さらに、仮想通貨同士の交換時の課税を繰り延べ、つまり、仮想通貨を別の仮想通貨に交換した時点では課税せず、それを法定通貨に変えたときにまとめて課税することを検討するよう求めています。ただし、この点についてはステーブルコインを含むべきかなど、さまざまな議論の余地があるため、将来的な要望として提出されています。
これら全ての提案は、政府が次世代のインターネットであるWeb3を成長戦略と位置づけ、国内の暗号資産業界の競争力を強化するために必要な税制改革と捉えられています。

※横山公認会計士事務所では、本サイトに記載した情報に関しては、投稿時点の法令及び会計基準に基づき記載しています。
内容については、万全を期しておりますが、記事投稿時点とは法改正等により異なる法施行状況になっている場合があります。
記事の内容等の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
About Us


〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1-23-1-504 TEL 043-224-1883 FAX 043-222-4654
本千葉駅東口駅前
1-23-1-504, Nagazu, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0854, Japan Tel +81 (43) 224 1883 Fax +81 (43) 222 4654